『 貴婦人Aの蘇生 』 [O.Y]
小川洋子 著 / 朝日新聞社
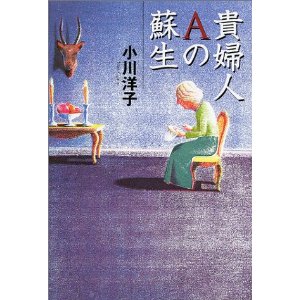
北極グマの剥製に顔をつっこんで絶命した伯父。法律書の生き埋めになって冷たくなっていた父。そして、死んだ動物たちに夜ごと刺繍をほどこす伯母。この謎の貴婦人は、はたしてロマノフ王朝の最後の生き残りなのか?
ユーリ伯母さんが、ロマノフ王朝の最後の生き残り、アナスタシア皇女なのか?
(アナスタシアというのは、ロシア語で 蘇生、という意味もあるそうです)
その真実は、学者たちに 検証されても、該当する証拠を 提示されたとしても
そのこと ついては、私の関心は、どんどん うすれていった。
語り手・私とニコの、伯母さんにむける やわらかな眼差し、ニコの抱える症状に
伯母さんと『私』が 寄り添う姿勢や 理解する気もち。 そうした、それぞれの想いを
垣間見るだけで、(時に、切なさも かんじるけど) 優しい気もちになれる。
剥製コレクター、オハラの動向を 説明するのは控えるが、彼の書いた レポートで
この本は 幕を閉じるので、彼の印象も 大きく残る。
憶測でしかないが、この物語の紡ぎ手である 著者は、この本を手にする 読者達を
最も離れたところで 俯瞰し、皇女であるのか ないのかという事実を 追ってゆく事に
対して、あまり主眼を おく必要はないですよ、と思っているのではないかと、感じた。
著者が 過去に書いた本の中では、からだの一部を失ったり、からだの一部だけが
展示品として、永遠に この世に残されたり、という 印象的な物語すら ある。
( 『 詩人の卵巣 』 だったか。)
そして、モチーフ(?)の 終着点というか、その極みのように 思えたのが、滅びたと
いわれている一族の、生存者が もしこの世にいたら…? という、人物そのものを
そのテーマとして 辿り着いたのではないだろうか、という 印象を 持った。
(エッセイとかから、この本について書かれたものを、探してみたい)
ロマノフ王朝が、革命によって崩壊され、その一族は、皆 処刑されたと伝わっている
らしいが、完璧な公表をなされていない ということで、色々な憶測がでているそうだ。
王朝は 確かに存在し、その一族は 高貴な人々として この世に 現存していたのに
情勢が変わり、高貴であった人々は、粗末な扱いを 受けるようになり、その果てに
命まで 奪われてしまった。
様々な歴史の中で、形勢が逆転して、信じられていたものが 意味のないものに 変化
してしまったり、また 恐ろしい妄執の末、人々が悪魔と化してしまったような時代の
ある一面だったり、この世界の 基盤の脆さ、確実性のなさ、確かなものの曖昧さ などを
なぜか 読みながら考え、こわくなったりもした。
皇女という位を 剥奪されたとしても、もし生存していたのならば、それは良かったこと
とも思えるが、この本に出てくる、剥製達と 重ねて考えてしまうと、もう 亡き姿となって
いたはずの人間が、その後、生きてゆかなくては ならない運命にあることの、過酷さや
残酷さを、どうしても 感じずにはいられなかった。
本来、野生で 死をむかえた動物は、かたちを残さず 土にかえるのだ。
剥製にされる動物は、唐突に 命を奪われ(全てではないだろうが)、生きていた時とは
違う、半分は(毛皮やらの)本物で、半分は(詰め物やらの)偽物という、奇妙な形に
させられてしまう。
見るほうが、すぐにその違和感を 察知できるのが、瞳ではないだろうか。
剥製に埋め込まれた 義眼が、剥製が異様なものであることの 象徴のように、幼い頃
から 思っていた。
博物館で、自分が 剥製たちに囲まれている時、気もちが ぞわぞわして、地に足が
ついていないような、イヤな不安感に苛まれたのを 私は思い出した。博物館に行けば
きっと 今もそうなるだろうな。 あれは、異様な光景ですよ、やっぱり。
本の巻末にある 参考文献を見て、ふと思った。
著者は 史実をもとに 着想を得た 物語で、ユーリ伯母さんという人物を、本の 読者に
出逢わす。私が 詳しく知らなかった、アナスタシアの存在を知る きっかけとなったのは
この物語に登場する、伯母さん。
史実と物語が、まざりあう妙と、それを 生み出す作家。物語って、興味深いですね。
読後、本当に、アナスタシア皇女かもしれないし、違うのかもしれないということを
さしおいて、伯母さんのもつ、透明で それでいて深いブルーの美しい瞳、それだけは
まぎれもない真実で、それだけで もう いいのだ、という気もちなった。
そして、『 独創的 』というのは、こういう作品のことを いうのだろうなと思い、改めて
著者にたしいて 敬意を抱いた。
タグ:貴婦人Aの蘇生



